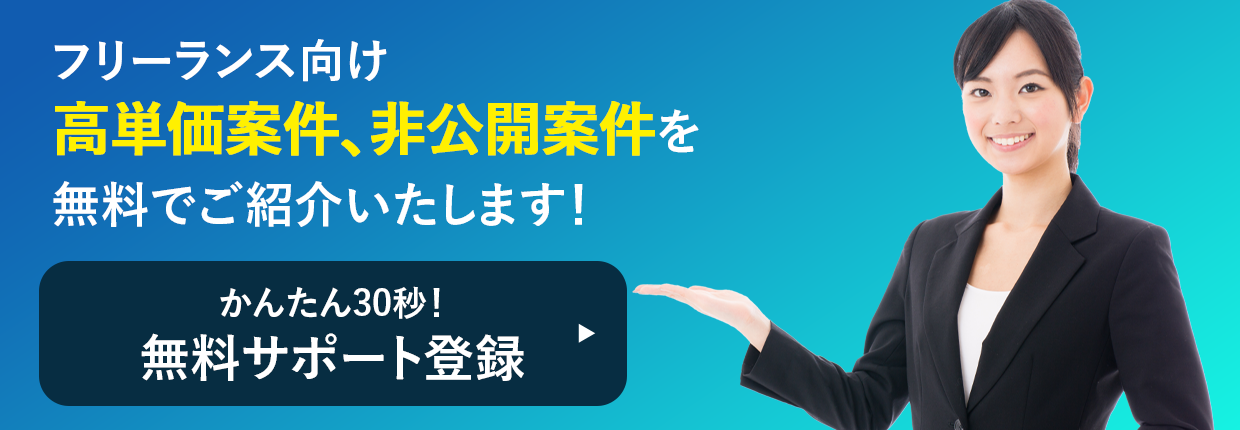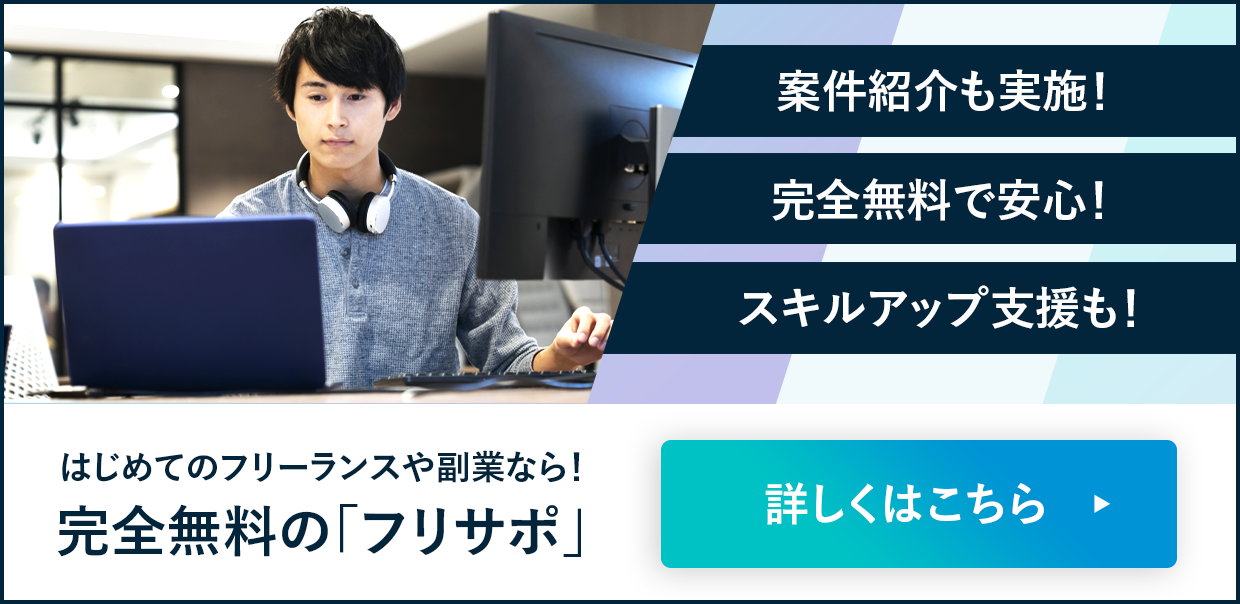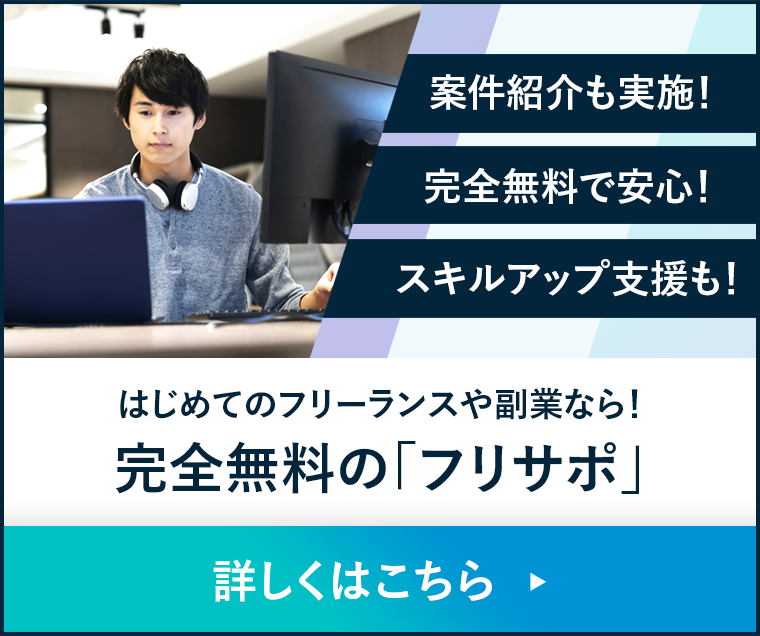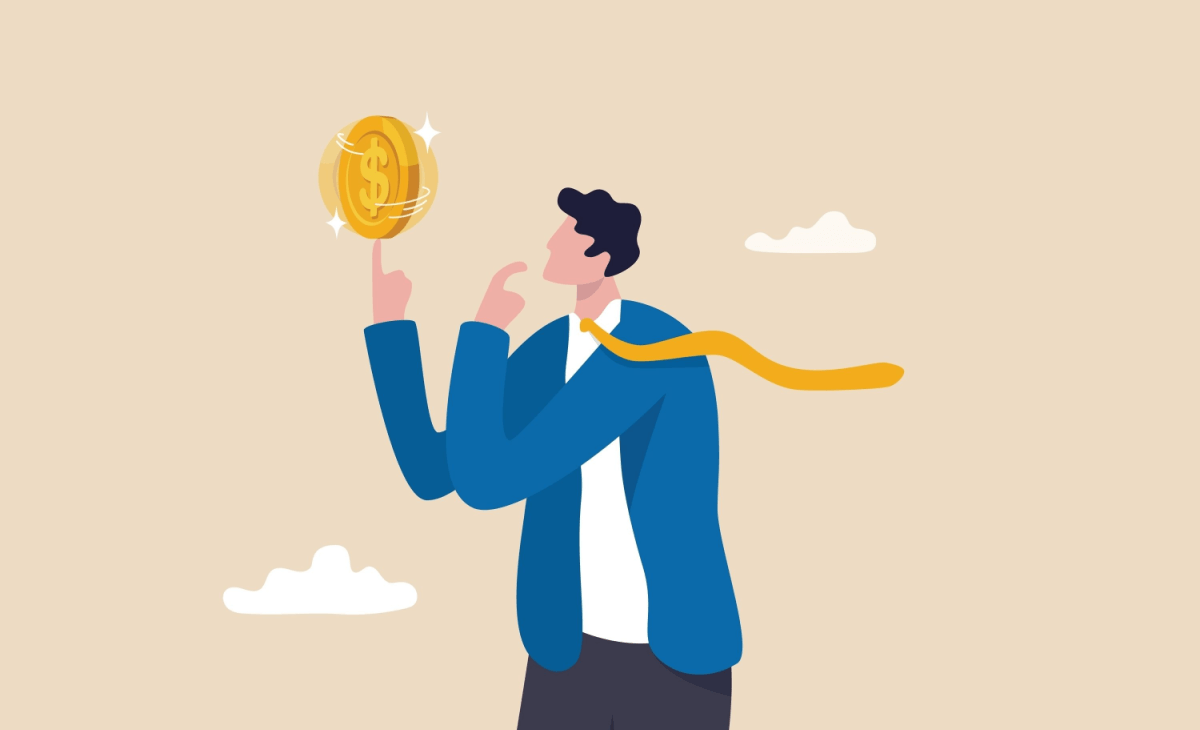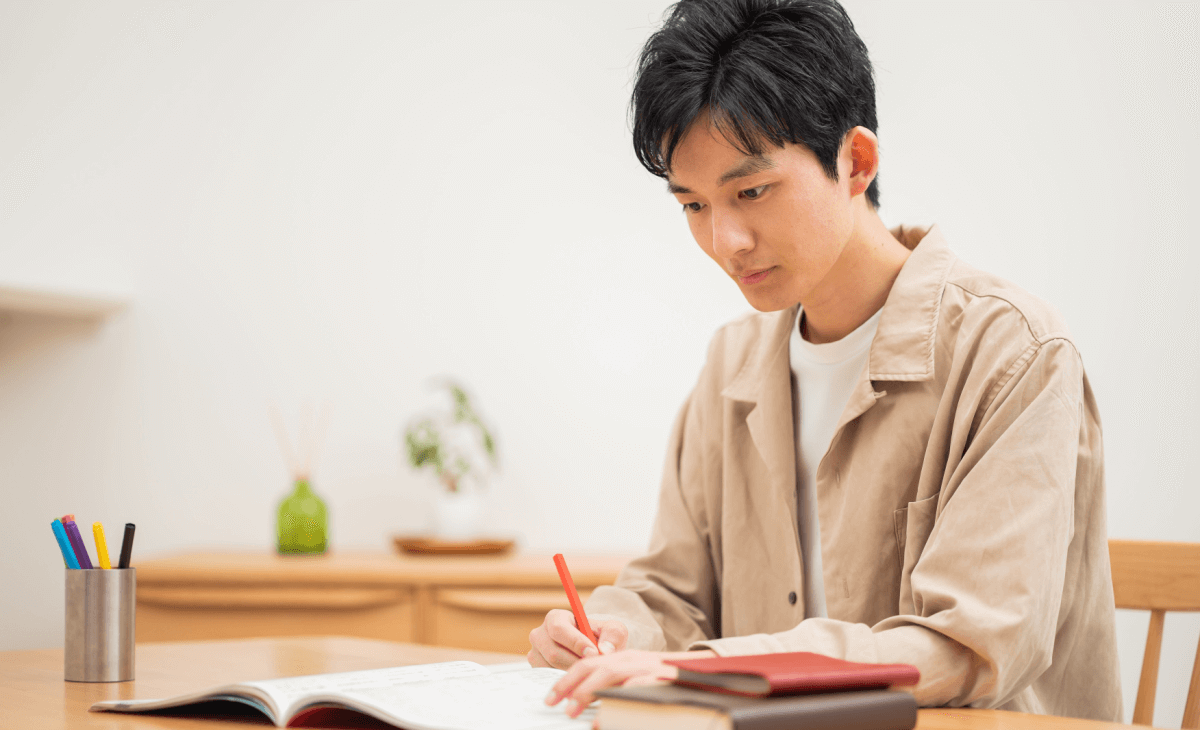Linuxエンジニアの需要って?仕事内容に年収事情、おすすめ資格や将来性もチェック!
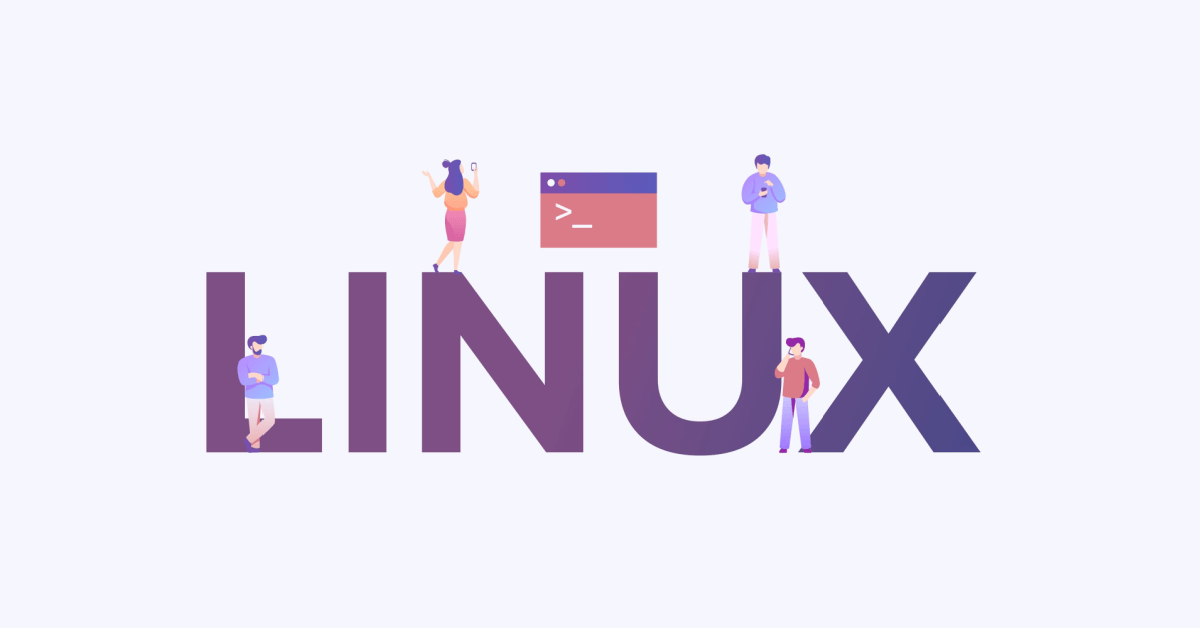
Linuxエンジニアは、ITインフラの設計・構築・運用などを担うインフラエンジニアの職種の1つで、Linuxを専門に扱うエンジニアのことです。
1つのOSに特化した職種ではありますが、Linuxは多くのシステムで採用されているOSであるため、Linuxエンジニアは需要の高い職種となっています。
この記事では、Linuxエンジニアの仕事内容や年収事情、おすすめの資格、将来性などについて解説します。
目次
Linuxとは
Linuxは、フィンランドのリーナス・トーバルズ氏によって1991年に開発されたOSで、現在はサーバーや業務アプリケーション、組み込みシステムなどで広く利用されています。
LinuxはUNIXを参考にして作られたOSですが、UNIXを含む他のOSと大きく異なる点として、オープンソースのソフトウェアであるという特徴があります。そのため、基本的には無料で利用することができ、改変や再配布も自由に行うことが可能です。
他のOSと比較して、導入コストを大幅に削減できることから、多くの現場で採用されています。
Linuxの利用されている分野
Linuxは様々なシステムやサービスにおいて利用されていますが、特にアプリケーションや組み込みシステム、サーバーのOSに利用されることが多くなっています。
それぞれの分野について、以下に詳しく説明します。
アプリケーションの開発
Linuxを利用することで、Linux上で様々なプログラミング言語を用いて業務用アプリケーションやWebアプリケーションを開発することが可能となります。
Linuxは、他のOSと比較すると、無償で導入することができるというコスト面に加えて、豊富なデバイスドライバやミドルウェアが用意されているというメリットもあります。
また、Linux向けの統合開発環境も複数揃っており、開発用途に合わせて活用することができるため、アプリケーションの開発の際に採用されることが多くなっています。
組み込みシステム開発
Linuxは、家電などの電子機器の中に組み込まれる、組み込みシステムの開発にも用いることができます。
当初はコンピュータ向けのOSであったLinuxですが、ソースコードを自由に書き換え、組み込みシステム向けに最適化することができる柔軟さから、徐々に組み込みシステム開発にも使われるようになりました。
現在は、スマートフォンのOSや、テレビ、デジタルカメラ、カーナビなど様々な機器にLinuxが使われています。
サーバーの構築
Linuxを用いてサーバーを構築するのは、Linuxの代表的な使い方となります。
LinuxでWebサーバーやデータベースサーバー、メールサーバー、FTPサーバーなど様々なサーバーを構築することができます。
サーバーOSとしては他にUNIXやWindowsなどがありますが、いずれも有償となるため、開発コストを抑えられるLinuxは採用されやすいサーバーOSです。
Linuxを扱えるインフラエンジニアの需要が高い
LinuxはサーバーのOSとして利用されるため、ITエンジニアとしてLinuxのスキルは身につけておくと有用です。なかでもインフラエンジニアは、ITインフラであるサーバーやネットワークの設計・構築・運用保守を担うため、Linuxの知識は必須となります。
従来のオンプレミスで構築するシステムだけではなく、最近はクラウド環境にシステムを構築するケースが非常に増えています。クラウド環境の開発においても、Linuxが採用されるケースが多いため、Linuxを扱えるインフラエンジニアの需要は現在も非常に高くなっています。
Linuxを扱うインフラエンジニアの仕事内容
Linuxを扱うインフラエンジニアの仕事内容は、具体的にどのようなものになるのでしょうか。
インフラエンジニアの業務内容である「設計」「構築・開発」「運用・保守」のそれぞれのフェーズについて、仕事内容を説明します。
設計
システムの要件を実現するためのシステム構成やディスク等の容量について、予算や開発期間を加味しながら設計を行います。
ここでは、サーバ台数などの物理的な構成に加えて、使用するハードウェア、ソフトウェアなども選定します。LinuxはOSの種類がいくつかあるため、どれを採用するのかということや、基本的なパラメータの設定値なども検討し、それぞれの内容を設計書としてまとめます。
構築・開発
構築・開発のフェーズでは、設計書をもとにして、ITインフラの構築・開発を行います。
サーバーやネットワーク機器などの物理的な設置から、OSやミドルウェアのインストール、パラメータの設定等までを行い、システムの礎となるインフラを構築します。
また、構築・開発を行った後には、インフラ環境が設計書通りに構築できているかのテストも行います。
運用・保守
ITサービスがリリースされた後は、ITインフラを安定的に稼働させ続けるための運用・保守を行います。
運用・保守の計画に基づいたシステムの起動・停止やソフトウェアのアップデート、パッチ適用などのメンテナンス作業、障害発生時の緊急対応などが業務内容となります。ITインフラに障害が発生すると、多くの場合サービスが正常に稼働しなくなるため、非常に重要な作業です。
Linuxエンジニアの年収事情
Linuxエンジニアの収入はどの程度となっているのでしょうか。
複数の求人サイトを参考にすると、Linuxエンジニアを含むサーバーエンジニアの平均年収は460万円程度となっています。
ただし、サーバエンジニアの中にも様々な職種があり、例えば決められたマニュアルに従ってサーバーの監視作業を行なうような仕事は、報酬額が低めとなることが多いです。
逆に、Linuxについて豊富な知識を持ち、システムの設計や構築を主体的に行うことのできるエンジニアは、上記の平均年収よりも高めの報酬を狙うことが可能となるでしょう。
また、Linuxエンジニアとしての実務経験があれば、フリーランスとしての独立も目指せます。フリーランスの場合は案件ごとの報酬になるため、スキルや実績があれば会社員と比較しても高年収を狙いやすいという特徴があります。Linuxエンジニアとして年収アップを狙っているのであれば、フリーランスになることを検討してみるのも一つの選択肢と言えます。
▼Linuxエンジニア向けのフリーランス案件情報はこちら!(登録無料)
https://www.bigdata-navi.com/item/tool/tool-42/
Linuxエンジニアとしての需要を高める方法
Linuxエンジニアとしての需要を高めるためには、スキルの向上や経験の積み重ねが重要です。市場のニーズを的確に捉え、柔軟に対応できる力を身に付けましょう。
ここでは、Linuxエンジニアとして需要を高めるための具体的な方法を4つ紹介します。
- プログラミング言語(Python、Perl、 Rubyなど)スキルの習得
- クラウド環境でのシステム構築・運用スキル
- 上流工程の経験を積む
- コミュニケーション能力と問題解決能力を身につける
プログラミング言語(Python、Perl、 Rubyなど)スキルの習得
プログラミング言語のスキルは、Linuxエンジニアとして活躍する際に役立ちます。中でもPythonは、分かりやすい構文と豊富なライブラリが魅力で、サーバー管理やタスク自動化に活用可能です。
また、Perlはテキスト処理が得意で、システムログの解析などで力を発揮し、RubyはWebアプリケーションの開発に向いています。まずは1つの言語から始め、徐々に幅を広げることで、より多くのプロジェクトに対応できるエンジニアを目指しましょう。
クラウド環境でのシステム構築・運用スキル
クラウド環境は、近年のITシステム運用で欠かせない存在となりつつあります。Linuxエンジニアにとって、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azure・GCP(Google Cloud Platform)などのクラウドサービスを扱うスキルは、需要を高める大きな武器です。
仮想サーバーの管理やストレージの最適化、ネットワーク設定の機能を使いこなせれば、エンジニアとしての信頼を高めることにつながるでしょう。また、基本操作だけでなく、セキュリティや障害対応の知識を深めることが、より需要の高いエンジニアになるためのポイントです。
上流工程の経験を積む
需要が高いLinuxエンジニアになるためには、上流工程の経験を積むことも大切です。上流工程とは、システムを作る前の準備段階で行われる要件定義や設計を指し、クライアントの要望をシステム設計に落とし込むスキルが求められます。
この経験を積むことで、課題を解決する力や全体を見通す視野が身に付くため、プロジェクトの方向性を決められる存在として評価されることが多いです。その結果、リーダーやマネージャーといったポジションへの道も開け、キャリアの幅が一気に広がるでしょう。
コミュニケーション能力と問題解決能力を身につける
Linuxエンジニアとしての成功には、技術スキルだけでなく、コミュニケーション能力と問題解決能力も必要です。エンジニアの仕事は、他のチームメンバーやクライアントと連携する場面が多く、正確に情報を伝えたり、意見を調整したりする力が求められるからです。
また、問題解決能力は、単にエラーを修正するだけでなく、再発を防ぐ根本的な対策を考える力も含まれます。こうした能力を鍛えるには、日常業務において相手の意図を正確に理解し、自分の考えを簡潔に伝える訓練を意識的に行うことが有効です。
需要の高いLinuxエンジニアはフリーランスとして活躍もできる
多くの企業がコスト削減や柔軟なシステム構築を目指し、Linuxを採用するケースが増加しています。その結果、Linuxに精通したエンジニアの需要が高まっているため、フリーランスとしての活躍の場も広がっています。
オンプレミスやクラウド環境でのサーバー構築や運用・アプリケーション開発など、フリーランスとしての案件は様々です。市場のニーズに応える需要の高いLinuxエンジニアを目指すことで、キャリアの幅を広げることに役立つはずです。
Linuxエンジニアにおすすめの資格情報
Linuxエンジニアになるために必須の資格はありませんが、Linuxエンジニアとして活躍するために、資格の取得を目指すのもよい方法です。
以下に、Linuxエンジニアにおすすめの資格を3つ紹介します。
Linux技術者認定試験(LinuC)
LinuCは、LPI-Japanの運営する、Linuxの技術力を証明するための認定試験です。
Linuxに特化した資格ですので、まず最初に取得を目指す資格としてはLinuCがおすすめです。
レベル1〜3の3段階に分かれているため、未経験の方はLinuxの基本的な構築・運用ができるレベルである、レベル1からの取得を目指しましょう。
オラクルマスター
オラクルマスターは、Oracle社が認定する、Oracle Databaseに関する知識が問われる資格です。
データベース関連の資格としては最も有名で、データベースに関する広い知識があることを証明できます。インフラエンジニアとして、データベースのスキルを持っていると、転職などで有利になります。
Platinum、Gold、Silver、Bronzeの4段階に分かれていますが、特にSilver以上のレベルが高く評価されやすいため、まずはBronze からチャレンジし、Silverの取得を目指しましょう。
Cisco技術者認定資格
Cisco技術者認定資格は、Cisco Systems社が認定する資格です。
ネットワークの技術者としての知識やスキルを認定する代表的な資格で、難易度はCCIE(エキスパート)、CCNP(プロフェッショナル)、CCNA(アソシエイト)、CCENT(エントリー)の4段階に分かれています。
インフラエンジニアとしてネットワークに関するスキルがあることをアピールするのであれば、まずはCCNAの取得を目指すとよいでしょう。
Linuxエンジニアの需要と将来性
Linuxエンジニアをはじめとしたインフラエンジニアは、どの分野のITサービスでも必ず必要となる存在であるため、安定した需要があります。
現在、ITエンジニア業界は全体的に人手不足の状況であり、特にインフラエンジニアは人が足りないと言われています。
なかでもLinuxはオンプレミスのシステムに加えて、クラウド環境で構築されるシステム、組み込みシステム、アプリケーション開発など様々な用途に使われるため、今後も一定のニーズがあり続けることが想定されます。
そのため、Linuxの知識を身につけ、Linuxエンジニアとして活躍することは、将来にわたって安定したキャリアを築くことができる選択であるといえるでしょう。
AIを仕事にするためのキャリアノウハウ、機械学習・AIに関するTopics、フリーランス向けお役立ち情報を投稿します。

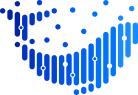 フリーランス求人を探す
フリーランス求人を探す